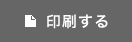OPAMブログ
「心の揺らぎ」、あるいは「我らが友、佐藤溪」
![]() 2018.03.08
2018.03.08

「心の揺らぎ」、あるいは「我らが友、佐藤溪」
−「歌心と絵ごころの交わり 二豊路 漂泊の画人 佐藤 溪 と 俳人 種田山頭火」展に寄せて
[ 迷う心 ]
「旅愁」とか、「郷愁」という言葉が、まず、浮かんでくる。( 大分にもかかわりのある、作家横光利一の『旅愁』からとった)
でもそうは言っても、それは、そう簡単なことでもないだろう。
大分合同新聞で、文化欄を担当している佐藤栄宏さんとは、よく話しをするが、彼の率直な意見に、時に驚くことがある。先日も館長室に来て、「佐藤溪、良いですねえ。なんかすごく、気持ちにぴったり来た。自分に絶対的な自信を持って生きている人はいるが、そうでない、なんか、行きあぐねている、生きながら迷っている人間の、心の襞がうまく、表現されている。詩もすごく良い。山頭火も、また生きることに苦しんで、悩んでいたが、佐藤のは、またそれとも、ちがう感じですね。」
余計なことを書くと、彼は美術の専門家でもなければ、たぶん、すごく小さい時からアートに触れて来たとも見えない。けれど、素直に率直に、身体ぜんたいで、作品に触れることが出来る、稀有な感受性を持っていて、私もしきりに共感するのである。
不思議なことにというか、むしろ当たり前なことに、彼の感想は、佐藤溪の芸術の本質、さらには山頭火のそれを、ピタリと見抜いている。
彼が言いたかったのは、山頭火の性格は、もっと激しく破綻的、破滅型、その詩情も時に雄渾であって、ちょっと私ども、通常の生活人には、とうてい真似出来ないが、佐藤溪は、そこらによく居る人のようで、自分たちにごく近い、「ちょっと変な人」として身近に感じられる、ということだろう。
これも、私の持っている感想とまったく同じなのである。
迷わない人間なんて居ないし、居たって、面白くも何ともないからだ。
迷い、戸惑う、人間。
その鏡が、佐藤溪であって、私どもの日日のちょっとした、心の絢というか、襞がぼんやりと映しだされていくような、そんな詩魂をもった絵画群なのである。
絵で「下手」か、「上手い」か、人はよくこだわるが、自分で描いてみるとまず分かることだが、「下手」と思うのは、「何か自分じゃないな」とその絵と自分の心を照らして思ったからで、「オーッ、行けてる、俺が、私が良く出てる」と感じたら、もう、「上手い、下手」なんて気にならなくなる。
[ 彷徨う心、放浪 ]
それに、何より放浪癖。
旅行の嫌いな人(私は、じつは、「独り遊びが好き」で、用の無い時は、積極的に、「出不精の引き篭もり型」だが、それを知っているのは、女房ぐらいしか居ないだろう)は、まず居ない訳であって、そうすると、人間皆、「放浪者」、ということにもなる。
亡くなった仏文学者で、ゴーギャンのタヒチ行や元祖アウトサイダー作家、郵便配達夫シュヴァルなどを書かれ、ご自身でも沖縄や先島がお好きで旅行され、そういうのが「文明の自己否定性」なのだ、と書かれておられた、岡谷公二先生じゃないが、「やはり、旅に出ないと、誰しも、血が澱む」のだと思う。
つまり、旅することは、アートすることと、同じではないか。
畏友の文化活動家、熊倉敬聡も、「古代ローマ?から、抑圧を社会から受ける人間は、血が澱んでいるの( STASIS )で、その「外へ出る」( EX )、つまり「澱みの外へ出る」( EX-STASIS )こそ、アートの原義で、エクスタシーの語源だよ」と言っていたのを、思い出す。
佐藤溪は、私と同じ、広島県の奥、熊野筆で有名な熊野の出身だ。
じつは、山頭火と佐藤溪とは、歳にして三十いじょうの隔たりがあって、じっさい交わる時期、時点も無いのだが、私としては、そのほぼ中間に、古里尾道の(出身ではないが、たしか、女学校時代を過ごした)、林芙美子がいる。
よく知られたように、彼女のデビュー作にして、ちょうど、都市大衆化が激しく進もうとしていた、昭和の大ヒット作が、昭和五年、1930年に出た、かの『放浪記』である。
「私は古里を持たない。宿命的な放浪者である。」
正直に言って、この出だしは、殺し文句のように、以降の、この昭和の三十年代、あの輝ける戦後の、「懐かしい」時代に、地方の小都市に生まれて、成人して後の半生、四十年余を、この東京という、面白いんだか、つまらないんだか、訳の分からない、メガロマニアックな怪物の街に住むことになる少年、私の、生涯、脳裏に焼きつくことになった。
焼きついたばかりではなく、後にかかわることになる、近代芸術、モダン・アートの、その宿命の根にあるものとして、やがて認識されるようになったのである。
この当時、昭和の初期は、地方から出てきた私ども労働者、サラリーマン層の元祖たる人人で東京が溢れ、関東大震災以降のインフラ整備も整って、巨大都市化、大衆化がはじまっていた。その先鞭として、登場して、東京における「地方出身者」の思いを一心に集めて、共感を呼んで、大ヒットしたのが、この『放浪記』であった。
川本三郎さんの、素敵な『林芙美子の東京』に詳しいが、そこに活写されていたのは、元気いっぱいの女の子、林芙美子は、カフェーの女給をしながら?勉強し、金が無くて、東京を歩き回り、恋人とも上手く行くようで行かない、『青春の蹉跌』そのものを生きる若き女性、彼女が、いっぽうでは、そこらの雑踏から、湧きあがっている「美味しい匂い」に引き寄せられてゆく、「肉体の賛歌」でもあった(この辺、川本説の借用)。
そこには、また、行間行間に、一抹のペーソス、哀愁があふれていた。
佐藤溪の絵には、都市、東京も、地方の街や海辺も、描かれている。
それはまた、近代芸術に燦然と輝く、松本竣介や、異端の画家、長谷川利行などの絵にある、ある種の痛みや、哀愁と似たようなものが、また漂う。
ただ、それはどんなに似ていても、佐藤溪その人じしん以外のものではない、唯一無二の、痛みや哀愁だったのである。
それが、昭和という時代の匂いだったような気も、私にはする。
人は、なぜ旅するのか、それもまた、人生が一つの旅であることを、確認するために、旅立つのだ、と私には思えて仕方ないのであった。
[ フラジャイルな、私ども、人間 ]
最近、どこでも、「弱さ」とか「フラジャイル=脆弱=ガラスの魂?」というのがもてはやされているようなので、それに迎合するようでちょっとなん何だが、それが当たっている部分は、佐藤溪にはたしかにあると思う。
やはり、佐藤溪は、私ども一人ひとりのなかにある、漠とした不安や、寂しさに、寄り添って、詩を書き、絵を描いた人だ。その場、その場の想いや、心の状態に正直に対峙している。
そういう意味で、私は、「私のなかに居る、佐藤溪」、あるいは、「心の友としての、佐藤溪」を激しく感じる。
まあそれも、仮定でしかないが、ある種の完成された作品、あるいは美のかたち、というものはあるだろうが、佐藤溪は、はなから、そんなものに無関心で、心の癒し、投影として素直に、そこいらにあったボール紙や鉛筆を手にとって、思いのままに描いていっている。
そう思って、自分にとって思い出すのは、古里尾道の洋画家、亀山全吉である。画壇の重鎮、ルノアール風の色彩豊かな風景画を描いた、小林和作が尾道に晩年住んだが、その弟分、という感じの、半抽象の絵描きだ。
亀山全吉の絵は、何とも、子供のなぐり描きのような、それでも青や黒で彩った、四角い家や、それが並んだ街、つまり、海岸から急な坂で山にのびあがる、家家が立て込んだ、尾道の路地だ。
それが、ヘタウマのような、クレーのような、デュビュッフェのような、厚塗りのなぐり描きで、小さな画面に犇いている。
全吉さんは、いつも、何か、ぼやーッとした、浮浪者のような、徘徊人のような風態(失礼!たぶんちがうだろうけど)で、町をフラついていたらしい。全吉さんは、尾道の小さな町を、日毎ブラブラ、小旅行して、その身体に染み込んで来る、「町の匂い」を、その時その時の気分で小さなキャンヴァスに、描いていったのだろう。
私は、そんな全吉さんが、絵描き本来の姿を伝えているようで、好きだ。
私の母は、町でそんな全吉さんをよく見かけた、という。
[ 山椒は小粒で、ピリリと辛い ]
こう、佐藤溪の生涯と画業を、簡単にくくる訳にもいかない。
けれど、今回の展覧会は、紋切り型の言葉を使うと、まさしく、「山椒は、小粒でピリリと辛い」を地で行ったものになっていて、発想者の立場から見ても、贔屓目ではなく、すごく面白い展示になっていると思う。年度末で、ちょっと会期が短いのが残念だが、ぜひともよりたくさんの人に見ていただきたい、と願っている。
佐藤溪については、美術館準備の時からかれこれ七、八年ほど前から、見たりしていて、その経緯やら、真骨を注いでその顕彰に尽くされて来られた、別府の、聴潮閣を営んでおられた高橋鴿子さんの情熱を良く知っていたので、何かのチャンスに県立美術館としても、お手伝い出来ないか、と考えて来たものだが、ここでは詳述しない。
その佐藤溪との、「出会い」が絶妙なのである。
実際に、調査や構成を担当してくれたのは、OPAMの吉田浩太郎学芸員で、私事だが、慶應義塾の後輩、私のように仏文学を志して挫折して元々好きだった美術に鞍替えした半端者とちがって、日本美術の近世をバッチリ学んだエリートである。ことに、いろいろな蒐集家の方や研究者の方の協力、支援を仰ぎながら、種田山頭火の資料の発掘に頑張ったし、また新鋭の梶原麻奈未学芸員も、懸命にサポートして、成ったものである。
新見 隆(にいみ りゅう)
県立美術館長
武蔵野美術大学芸術文化学科教授